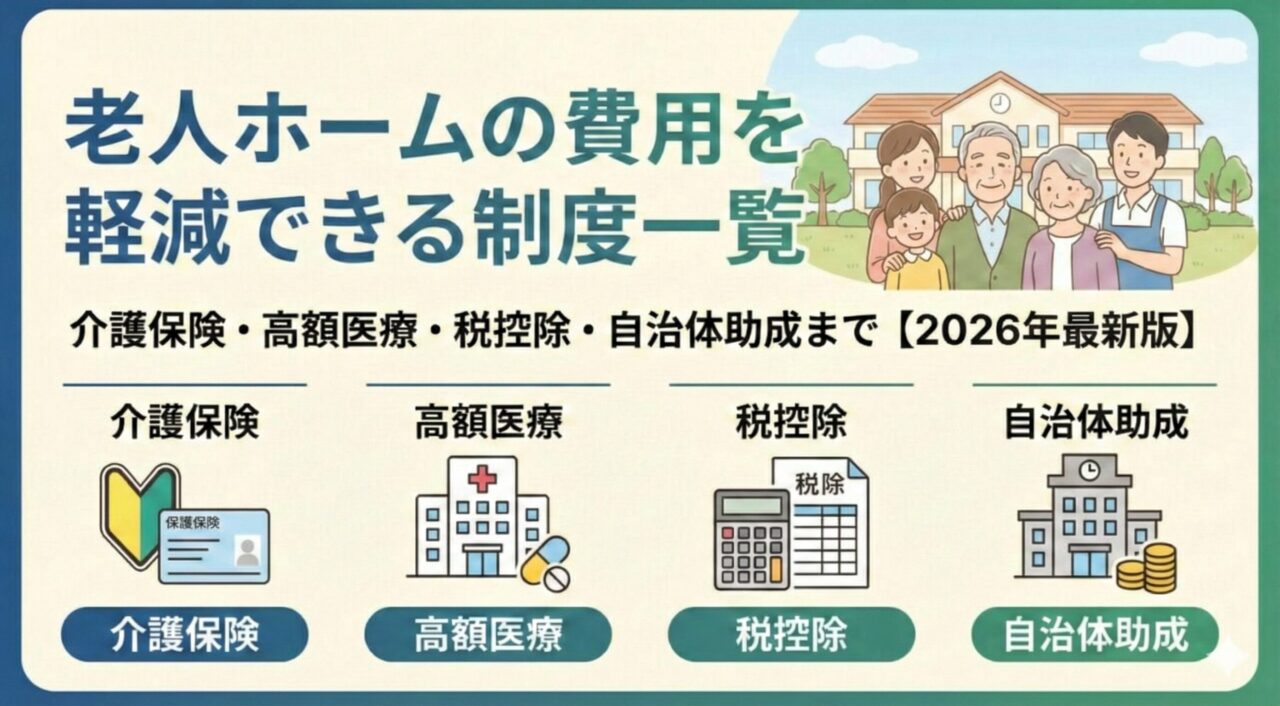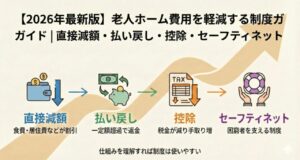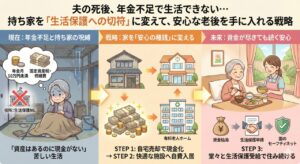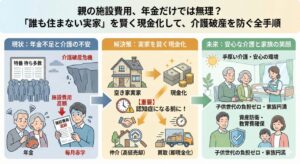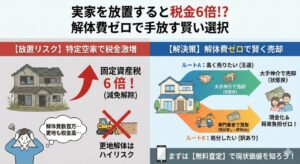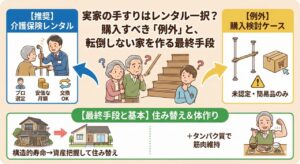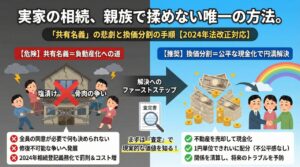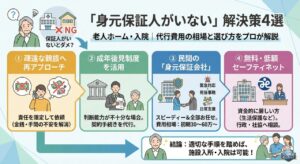老人ホーム費用の不安をどう解消する?
「親を老人ホームに入れたいけれど、費用が心配」「年金だけでは払えそうにない」
介護の現場では、こうした声を本当に多く耳にします。
厚生労働省の調査によると、有料老人ホームの平均月額費用は23.1万円、特別養護老人ホームでも12.5万円 にのぼります。
(出典:厚労省「介護サービス施設・事業所調査 2023」)
この金額を年金や貯蓄から支払うのは容易ではありません。
しかし、日本には 介護保険制度・医療制度・税制上の優遇・自治体の助成制度・生活困窮者向けセーフティネット と、多くの仕組みが存在します。
問題は、それらが「複雑で分かりにくい」こと。
結果として「本当は使える制度を使えていない」ケースが非常に多いのです。
そこで本記事では、老人ホーム費用を軽減できる制度を 種類別に整理し、網羅的に解説。
まずは全体像を把握し、その上で「施設別の記事」に飛んで詳細を確認できるよう構成しました。
介護保険制度による軽減
老人ホーム費用を考えるとき、最も基本となるのが 介護保険制度 です。
65歳以上で要介護認定を受けた方であれば、介護保険サービスを1割〜3割負担で利用できます。
しかし、それだけではありません。
介護保険の中には、さらに 費用負担を軽減できる仕組み が複数用意されています。
代表的なのは「特定入所者介護サービス費(補足給付)」と「高額介護サービス費」です。
特定入所者介護サービス費
老人ホームの費用で特に大きいのが 食費と居住費 です。
この負担を軽くしてくれるのが「特定入所者介護サービス費」、いわゆる 補足給付 です。
- 対象施設:特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院など
- 対象者:住民税非課税世帯など、一定の所得・資産要件を満たす人
- 軽減内容:居住費・食費の自己負担額が定額まで引き下げられる
- 申請窓口:市区町村の介護保険担当課
- 必要書類:課税証明書、年金額のわかる書類、預金通帳コピーなど
月額で見ると 数万円〜数十万円の削減 になるため、非常に大きな制度です。
注:令和7年(2025年)8月から、老健(その他型・療養型)や介護医療院(Ⅱ型)の室料相当額控除等に伴い、居住費の基準に見直しがあります。
お住まいの自治体の最新案内でご確認ください。
高額介護サービス費
介護保険サービスを使うと、利用料の1〜3割を自己負担します。
しかし、利用量が多くなると月に数万円〜十数万円の負担になることも。
そんなときに上限を設けてくれるのが「高額介護サービス費」です。
- 内容:1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額が、所得区分ごとの上限額を超えたとき、超過分が払い戻される
- 上限額の例(70歳以上・2026年時点):
- 一般所得世帯:月44,400円
- 住民税非課税世帯:月24,600円
- 現役並み所得世帯:月93,000円or140,100円
👉 要介護度が高く、サービス利用が多い人ほど恩恵を受けられる制度です。
医療制度による軽減
老人ホームに入居しても、医療費は必ず発生します。
風邪や慢性疾患の治療、入院、薬の処方など、介護とは別に医療費を支払う必要があります。
ここで家計を守ってくれるのが 医療保険の高額療養費制度や難病・障害者医療費助成 です。
これらの制度を理解しないまま老人ホーム生活に入ると、「介護費用と医療費の二重負担」で生活が破綻する危険すらあります。
まずは、全国で共通して利用できる代表的な制度を整理しましょう。
高額療養費制度(高額医療費制度)
「高額療養費制度」は、医療費の自己負担が一定の上限を超えたときに払い戻される制度です。
老人ホームで暮らしていても、通院・入院・投薬などで医療費はかかりますが、この制度を使えば青天井にはなりません。
- 対象者:国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療制度に加入している人
- 内容:1か月の医療費の自己負担額に上限を設定し、超過分を払い戻し
- 上限額(70歳以上・2026年時点)
・一般所得者:57,600円(外来18,000円)
・低所得世帯(住民税非課税):24,600円
・現役並み所得:80,100円+医療費の1%
👉 高齢者の場合は「外来の上限18,000円」が特に大きなポイントです。
毎月複数回通院しても、それ以上は支払わなくて済む仕組みです。
注意点:
- 医療費の自己負担分だけが対象で、食費や差額ベッド代は対象外
- 払い戻しには「支給申請書」の提出が必要な場合がある(自治体による)
高額医療・高額介護合算療養費制度
高齢者は医療と介護の両方を同時に使うことが多くあります。
そこで重要なのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。
- 内容:毎年8月〜翌年7月までの1年間で支払った「医療+介護」の自己負担の合計額に上限を設け、超過分を払い戻す
- 上限額(世帯単位)
・一般世帯:56万円程度
・低所得世帯:31万円程度
👉 例えば、介護費用で月44,000円・医療費で月30,000円を支払った場合、年間で大きな額を超えることがあり、この制度でまとめて返還されます。
申請の流れ:
- 医療保険者(国保・健保組合など)または自治体の介護保険課に申請
- 介護費用・医療費の支払い証明を提出
- 審査後、返還金が支給
指定難病医療費助成制度
「指定難病医療費助成制度」は、国が指定する348疾病の難病に該当する人が使える制度です。
- 対象者:医師の診断で難病と認定され、受給者証を持っている人
- 内容:医療費の自己負担割合が原則2割に軽減され、さらに月額の上限額が所得に応じて決まる
- 上限額の例
・住民税非課税世帯:2,500円
・一般所得世帯:10,000〜20,000円程度
👉 難病を持つ方は医療費が高額になりがちですが、この制度を利用すれば毎月の医療費が一気に下がります。
重度障害者医療費助成制度(自治体ごと)
全国の多くの自治体では、「重度障害者医療費助成制度」を設けています。
- 対象者:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級など
- 内容:医療費の自己負担分を全額または一部助成
- 注意点:介護保険が優先されるため、介護サービス費は対象外
👉 自治体により名称や対象基準が異なるため、必ず「お住まいの市区町村」で確認してください。
高額医療・高額介護の上限早見表
| 区分 | 医療:高額療養費(月) | 介護:高額介護サービス費(月) | 医療+介護:合算(年) |
|---|---|---|---|
| 一般所得 | 57,600円(外来18,000円) | 44,400円 | 560,000円 |
| 住民税非課税(低所得) | 24,600円 | 24,600円 | 310,000円(※区分により異なる) |
| 現役並み所得 | 80,100円+1%/ 多数該当:93,000円・140,100円 | 44,400円 | 区分により異なる |
※ 数値は2026年時点の代表例。制度・区分により異なる場合があります。最新は保険者・自治体でご確認ください。

税制上の控除制度
老人ホームの費用負担を直接軽減するものではありませんが、税制上の控除を活用することで、実質的に支出を減らすことができます。
確定申告や住民税申告の際に適用できる制度を見逃してしまうと、本来受けられるはずの還付や減税を逃すことになります。
ここでは、代表的な税制上の制度を整理します。
医療費控除
「医療費控除」は、1年間(1月〜12月)にかかった医療費が一定額を超えた場合に、所得から差し引くことができる制度です。
- 対象額:年間10万円(または所得の5%)を超える部分が控除対象
- 控除できる上限:200万円まで
- 申告方法:確定申告で申告し、所得税や住民税が軽減される
老人ホームで控除対象となる可能性がある費用
- 医師による治療、診察費用
- 医師の管理下で行われる医療系サービス
- 処方薬代、治療に必要な医療機器費用
対象外となる費用
- 居住費・食費
- 介護サービス費(生活援助や身体介護)
👉 ポイントは「治療目的かどうか」です。医師の指導に基づいて行われた医療行為であれば控除の対象になることがあります。
障害者控除
「障害者控除」は、本人または扶養している家族に障害がある場合に、所得から控除できる制度です。
- 一般障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円(要介護度が高い場合や重度障害者の場合が該当することも)
- 同居特別障害者控除:75万円(同居して扶養している場合)
👉 老人ホームに入居している家族が障害者認定を受けている場合、扶養している子ども世帯も控除を利用できることがあります。
扶養控除
「扶養控除」は、親を扶養している子どもが利用できる制度です。
- 一般の扶養控除:38万円
- 老人扶養控除(70歳以上):48万円
- 同居老親等扶養控除:58万円
👉 老人ホームに入っていても「生活費を負担している」と認められれば、扶養控除の対象となります。
介護保険料控除
- 支払った介護保険料は、社会保険料控除の対象
- 全額を所得から控除できるため、結果的に税額が下がります
- 老人ホーム入居前後に支払った保険料も忘れず申告を
雑損控除(例外的だが有効)
あまり知られていませんが、災害・盗難などで介護や生活に関する資産が損害を受けた場合、「雑損控除」が利用できます。
例えば、災害で老人ホームに入居中の親の生活物品が失われた場合などが対象です。
税制を活用する際の注意点
- 医療費控除や扶養控除は、確定申告をしないと受けられない
- 控除を使っても、課税所得がゼロの場合はメリットが出ない
- 自治体によっては「住民税非課税」による別の優遇があるため、二重に確認が必要
自治体独自の助成・軽減制度
介護保険や医療保険は全国共通の仕組みですが、実際の生活費を大きく左右するのが 自治体ごとの独自制度 です。
市区町村レベルで追加の助成や軽減策を設けているところも多く、該当すれば家計の負担がぐっと軽くなります。
全国どこでも同じではなく、住んでいる地域によって受けられる制度が違うため、「自分の自治体には何があるのか」を調べることが欠かせません。
利用者負担軽減制度(自治体版)
多くの自治体では、介護サービス利用料を軽減するために「利用者負担軽減制度」を設けています。
- 内容:介護サービスの自己負担額(1割〜3割)の一部を軽減
- 対象者:低所得世帯(住民税非課税など)、資産要件あり
- 申請窓口:市区町村の介護保険課
- 必要書類:課税証明書、預貯金残高、介護保険証など
👉 公的な軽減制度に加え、自治体の判断でさらに利用料が下がるため、対象になれば月1〜2万円程度の軽減になることもあります。
社会福祉法人による軽減制度
自治体と連携して、社会福祉法人が独自に行っている軽減策もあります。
- 内容:介護サービス費用の1割〜2割を法人が軽減
- 対象者:低所得者、生活困窮者
- 確認方法:入居予定の施設が社会福祉法人かどうかを確認し、申請
👉 特別養護老人ホームは社会福祉法人が運営するケースが多いため、該当すれば積極的に利用したい制度です。
食費・居住費の追加助成
一部自治体では、国の「特定入所者介護サービス費(補足給付)」に加えて、独自に食費や居住費を補助しているところがあります。
例:
- 横浜市:「介護サービス自己負担助成」や「施設食費・居住費助成」あり
- 神戸市:「利用者負担軽減確認証」を交付し、食費・居住費を軽減
- 東京都23区の一部:生活困窮高齢者への独自助成(生活福祉資金を組み合わせるケースも)
👉 「国の制度で対象外になったが、自治体制度で救われた」というケースは少なくありません。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)への助成
老人ホームではありませんが、サ高住に入居する高齢者に対して、自治体が 家賃補助や入居支援制度 を設けている場合があります。
- 例:大阪市では「高齢者向け優良賃貸住宅」への家賃補助制度を実施
- 条件:収入制限や高齢者世帯であることが前提
👉 サ高住は比較的自由度が高いため、制度を利用すれば「老人ホームより安価に生活できる選択肢」となります。
生活関連費の助成(おむつ・交通費など)
自治体によっては、施設入居者や在宅高齢者を対象にした生活支援助成もあります。
- 紙おむつ代助成:月数千円分を支給(東京都内の一部区など)
- 通院交通費助成:外来や通院のための交通費を助成(地方都市に多い)
- 福祉用具助成:ベッドや車椅子のレンタル料を自治体独自で軽減するケースも
👉 小さな助成に見えますが、長期的にみると大きな節約につながります。
自治体独自制度の確認方法
- 市区町村役所の 高齢福祉課・介護保険課 に問い合わせる
- 自治体公式サイトで「高齢者福祉」「介護 負担軽減」「老人ホーム 助成」で検索
- 入居予定の施設に直接確認(施設側が最新制度を把握している場合が多い)
👉 制度は自治体ごとに名称も内容も異なるため、「自分の地域」での確認が必須です。
セーフティネット制度
介護保険や医療保険、自治体の助成制度を利用しても、なお支払いが難しい場合があります。
そんなときに最後の砦となるのが セーフティネット制度 です。
「生活保護」や「世帯分離」などを活用することで、経済的に追い詰められないように支援を受けられます。
生活保護制度
生活保護は、資産や収入が最低生活費を下回る世帯に対して、国と自治体が生活費を補填する制度です。
老人ホームに入居している場合でも、条件を満たせば利用できます。
- 対象:収入や資産が最低生活費以下の人
- 内容:生活扶助(生活費)、住宅扶助(住居費)、介護扶助(介護サービス費)、医療扶助(医療費)など
- 申請窓口:居住地の福祉事務所
ポイント
- 特別養護老人ホームや介護医療院などの公的施設では、生活保護による介護費用の全額補助が受けられることもあります。
- 有料老人ホームの場合、施設費が生活保護の基準を超えると利用できない場合があるため、施設選びの段階から確認が必要です。
👉 生活保護は「最後の選択肢」と考える人も多いですが、実際には高齢者世帯の受給者は珍しくありません。ためらわずに福祉事務所に相談することが大切です。
世帯分離による負担軽減
あまり知られていませんが、「世帯分離」を行うことで、老人ホームに入居する親の所得・資産のみで負担判定が行われ、介護費用が軽減される場合があります。
- 仕組み:住民票を親と子で分け、別世帯として扱う
- メリット:
・子ども世帯の所得を合算されないため、親が「低所得者」として軽減制度の対象になれる
補足給付や高額介護サービス費の対象になる可能性が広がる - デメリット:
・親の住民税・国民健康保険料の計算が変わる場合がある
・扶養控除や配偶者控除に影響するケースがある
👉 世帯分離は「必ず得になる」とは限りません。制度全体を見ながら、税理士や社会福祉協議会、ケアマネジャーに相談するのがおすすめです。
社会福祉法人による利用者負担軽減制度(セーフティネット枠)
介護保険サービスの利用料について、生活困窮者を対象に社会福祉法人が軽減する仕組みがあります。
これは国が定める「利用者負担軽減制度」とは別に、法人が独自に行うセーフティ支援です。
- 軽減内容:介護サービス費の1割〜2割を減額
- 対象者:低所得・生活困窮世帯
- 申請:入居する施設の窓口で直接申請
👉 特養など社会福祉法人運営の施設では、この仕組みがあるかどうか必ず確認しましょう。
福祉資金貸付制度(生活福祉資金)
「どうしても一時的にお金が足りない」という場合には、社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」を利用できます。
- 内容:介護費用や入居一時金などを、無利子または低利子で貸し付け
- 対象:低所得世帯、高齢者世帯
- メリット:生活保護に至る前の一時的な資金繰りとして有効
👉 返済義務はありますが、急な出費に対応できるため「制度をつなぐ橋渡し」として活用する人が多いです。
セーフティネット制度を利用する際の注意点
- 資産調査がある
→預金・不動産・生命保険などの資産があると、利用が制限される場合あり。 - 生活保護は原則最後の手段
→まずは介護保険・医療制度・自治体助成をすべて検討してから。 - 世帯分離は損得が分かれる
→子世帯の税制控除が減る可能性があるため、事前にシミュレーションを。
民間・貸付制度
ここまで紹介した制度は、主に「公的制度」でした。
しかし、実際の老人ホーム費用をまかなううえでは、民間の仕組みや貸付制度 を活用するのも有効です。
「制度を使っても足りない」「急な出費に対応できない」といったときに、資金を確保できる選択肢となります。
福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)
全国の社会福祉協議会では「生活福祉資金貸付制度」を実施しています。
これは、生活困窮世帯や高齢者世帯に対して、生活費や介護費用を無利子または低利子で貸付する制度です。
- 用途:老人ホームの入居一時金、介護サービス費の支払い、医療費の補填など
- 対象:低所得世帯、要介護者を抱える世帯
- 返済:長期分割返済が可能。場合によっては償還免除も検討される
👉 「生活保護に頼る前の一時的な資金源」として利用されるケースが多く、緊急時の選択肢として押さえておきましょう。
民間保険(介護保障付き)
生命保険や医療保険の中には、介護保障特約 がついているものがあります。
親がこうした保険に加入していれば、老人ホーム入居に合わせて保険金を受け取れる場合があります。
- 介護保険(民間):要介護2以上など条件を満たすと一時金または年金形式で給付
- 医療保険の介護特約:介護状態になったときに一時金が出るケースあり
- 終身保険の活用:解約返戻金や保険金を介護費用に充てる
👉 保険契約を確認せずに「使えるお金がない」と判断する人も多いため、必ず加入している保険をチェックしましょう。
火災保険・共済の特約
意外と知られていないのが、火災保険や共済に付帯する「介護費用特約」 です。
- 自宅での事故や災害で要介護状態になった場合に、一時金が支払われる
- 共済組合によっては「高齢者介護給付金」として医療費や介護費を補填
👉 適用範囲は狭いですが、該当すればまとまった資金を確保できます。
住宅金融支援機構「リバースモーゲージ」
高齢者が自宅を担保に資金を借り、死亡後に不動産を売却して返済する仕組みです。
- 用途:老人ホーム入居一時金、介護費用の支払い
- 対象:持ち家がある高齢者
- メリット:生活資金を確保しながら自宅に住み続けられる
- デメリット:不動産価値が低い地域では利用が難しい
👉 「親が家を持っているが現金が少ない」という家庭で選ばれるケースが増えています。
地方自治体の高齢者向け貸付制度
一部の自治体では、高齢者や低所得世帯向けに独自の貸付制度を設けています。
例:
- 東京都福祉局:「高齢者生活安定資金貸付」
- 大阪府社会福祉協議会:「緊急小口資金貸付」
👉 全国一律ではないため、住んでいる自治体で確認が必要です。
民間・貸付制度を利用する際の注意点
- 返済計画を立てる
→貸付制度は生活をつなぐ手段であり、返済義務がある場合が多い。 - 保険は契約内容を確認
→「介護状態」や「要介護度」の定義が契約ごとに異なるため要注意。 - リバースモーゲージは家族で相談を
→将来的な相続にも影響するため、子世帯も含めて話し合いが必要。
制度を使いこなすためのチェックリスト
ここまで紹介したように、老人ホームの費用を軽減する制度は数多くあります。
しかし「知っているだけ」では意味がなく、実際に自分の家庭で使えるかどうかを確認し、漏れなく申請することが大切です。
制度を使いこなすためには、次のステップを踏むと整理しやすくなります。
1. 所得・資産状況を整理する
ほとんどの制度は、所得区分や資産要件によって対象かどうかが決まります。
- 年金額(老齢年金・遺族年金・企業年金など)
- 給与や事業収入があるか
- 預貯金額、不動産、生命保険などの資産
👉 住民税課税か非課税かは特に重要で、補足給付や高額介護サービス費の判定に直結します。
2. 要介護認定・障害認定を確認する
制度を使うには、要介護認定や障害認定が前提になることが多いです。
- 要介護1〜5であれば介護保険サービスを利用可能
- 障害者控除や障害者医療費助成は、障害者手帳や療育手帳などが必要
👉 認定を受けていないと制度の対象外になるため、早めの申請が欠かせません。
3. 施設の種類を確認する
老人ホームと一口にいっても、種類によって使える制度は異なります。
- 特別養護老人ホーム(特養)→ 補足給付、高額介護サービス費
- 介護老人保健施設(老健)→ 医療+介護の両方に制度適用
- 有料老人ホーム → 介護保険の枠組み外の費用が多いが、医療費控除や扶養控除は対象になり得る
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)→ 家賃補助や自治体独自助成
👉 施設の選び方次第で使える制度が変わるため、「どの施設に入るか」を検討するときに必ず確認しましょう。
4. 申請に必要な書類を準備する
制度を利用するには申請が必要です。
特に以下の書類は共通して求められることが多いため、事前に準備しておきましょう。
- 介護保険被保険者証
- 健康保険証
- 住民税課税証明書、非課税証明書
- 所得証明(年金振込通知書など)
- 預貯金通帳の写し
- 障害者手帳や療育手帳(該当する場合)
- 医療費の領収書(医療費控除・高額医療の申請用)
👉 書類が不足すると申請が遅れるため、早めに揃えておくことが重要です。
5. 制度の申請先を把握する
制度ごとに申請先が異なります。
- 介護保険関係 → 市区町村の介護保険課
- 医療費関係 → 医療保険者(国保・健保組合・後期高齢者医療広域連合)
- 難病・障害 → 市区町村の福祉課、障害福祉課
- 生活保護 → 福祉事務所
- 貸付制度 → 社会福祉協議会
👉 「どこに相談すればいいのかわからない」ときは、まずケアマネジャーに相談するとスムーズです。
6. 申請期限・更新時期を忘れない
制度の多くは「認定証の有効期限」があり、更新を忘れると軽減が止まってしまいます。
- 負担限度額認定証 → 1年ごとに更新
- 難病医療費受給者証 → 毎年更新が必要
- 障害者医療費助成 → 自治体により更新あり
👉 カレンダーや家族共有アプリに期限を記録しておくと安心です。
7. 制度を組み合わせて最大限活用する
制度は単独で使うだけでなく、複数を組み合わせることで負担を大幅に減らせます。
例:
- 特養入居+補足給付 → 食費・居住費軽減
- + 高額介護サービス費 → 介護費上限補助
- + 高額医療費制度 → 入院費用補助
- + 医療費控除 → 税金還付
👉 ひとつの制度だけでは効果が小さい場合でも、組み合わせれば年間数十万円の差になることがあります。
まとめ:制度をフル活用して老人ホーム費用を抑える
老人ホームの費用は「高い」と言われますが、実際に請求される額がそのまま自己負担になるわけではありません。
国や自治体には多くの負担軽減制度が整備されており、条件を満たして申請すれば、月数万円〜年間数十万円規模で費用を減らすことが可能です。
制度を活用するために
- 必ず申請が必要
→ 多くの制度は「自動適用」ではなく、窓口に申請して初めて使える - 組み合わせて最大限の効果を出す
→ 介護・医療・税制を同時に活用することで、実質負担は大きく変わる - 情報収集を怠らない
→ 制度は改正・更新が多く、自治体独自の助成も頻繁に変わるため、年に一度はチェック