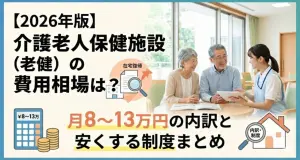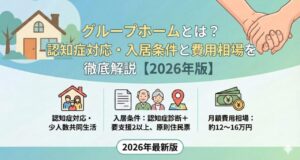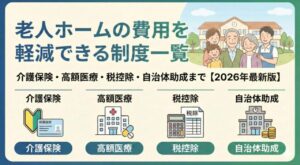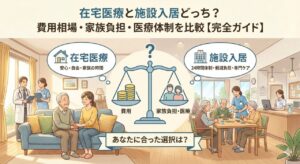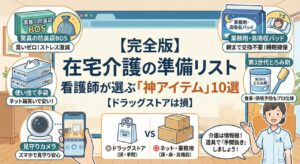「有料老人ホームに入居したいけれど、費用がどのくらいかかるのか不安」
「特養や老健より高いと聞くけど、実際の相場や制度がよく分からない」
そんな疑問を抱えるご家族は少なくありません。
有料老人ホームは民間施設であり、費用は15〜30万円/月が相場。さらに施設によっては数百万円〜数千万円の入居一時金が必要になることもあります。
特養や老健に比べると高額になりやすく、「どれくらい自己負担が発生するのか」が最大の関心事となるでしょう。
しかし実際には、介護保険制度や医療制度、自治体の助成を組み合わせることで、費用負担を軽減する方法が数多く存在します。
重要なのは、入居を検討する段階で「費用の構造」と「利用できる制度」を正しく理解しておくことです。
本記事では:
- 有料老人ホームの種類と特徴
- 費用相場と内訳(入居一時金・月額費用・介護サービス費)
- 費用を抑えるためのポイント
- 介護保険・医療制度・自治体助成の活用法
を分かりやすく整理しました。
👉 結論:介護保険+補足給付+高額療養費制度を組み合わせれば、施設によっては月額15万円も可能です。
有料老人ホームとは?【特養・老健との違いをわかりやすく】
有料老人ホームとは、民間企業や社会福祉法人が運営する高齢者施設で、介護・生活支援・医療連携を組み合わせて提供する住まいです。
特養や老健と違って公的施設ではないため、サービスの自由度が高い反面、費用が割高になりやすい という特徴があります。
2026年時点では全国に1万を超える施設が存在し、費用相場や制度利用の有無によって負担額は大きく変わります。
👉 有料老人ホームを検討するうえで大切なのは、この3つを理解しておくことです。
- どんな種類があるのか
- 他の介護施設との違い
- 入居までの流れ
以下で詳しく解説します。
基本的な役割
有料老人ホームは、民間企業や社会福祉法人などが運営する高齢者向け施設で、介護・生活支援・医療連携を提供する場です。
特養や老健が「公的施設」であるのに対し、有料老人ホームは「民間施設」であり、サービス内容や料金は施設によって大きく異なります。
特徴は、介護度や生活スタイルに応じて柔軟に選べることですが、施設によっては費用が高額になりやすい点が最大の課題です。
入所条件・種類
有料老人ホームは大きく3つのタイプに分かれます。
- 介護付き有料老人ホーム
・介護サービスが一体提供される
・要介護認定を受けた人が対象
・介護保険の「特定施設入居者生活介護」として指定を受けている - 住宅型有料老人ホーム
・生活支援サービス(食事・見守りなど)が中心
・介護が必要な場合は外部の訪問介護・訪問看護を利用
・自立〜軽度介護の人に多い
・医療対応型の住宅型有料老人ホームもある - 健康型有料老人ホーム
・食事や生活支援を提供、介護が必要になったら退去が原則
・現在は新設が少なく、数は限られる
👉 施設選びでは、自分や家族の介護度・将来の生活設計を踏まえた「種類の選択」が重要です。
他の施設との違い
有料老人ホームは「自由度が高い反面、費用も高額」という特徴を持っています。
| 項目 | 有料老人ホーム | 特養 | 老健 | サ高住 | グループホーム | 介護医療院 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主目的 | 介護+居住サービス | 長期生活 | 在宅復帰 | 自立+見守り | 認知症ケア | 医療+介護療養 |
| 入所条件 | 自立〜要介護 | 要介護3以上 | 要介護1以上 | 自立〜要介護 | 認知症で要支援2以上 | 要介護1以上、医療依存度高い人 |
| 医療体制 | 施設により差が大 | 看護師常駐 | 医師・看護師常駐 | 外部医療連携 | 基本外部対応 | 医師常勤・看護師常駐 |
| 滞在期間 | 長期可(終身型もあり) | 長期・終身可 | 原則3〜6か月 | 長期可(契約更新型) | 長期可(認知症退去あり) | 長期可・看取り対応 |
| 費用相場 | 15〜30万円/月+入居一時金 | 12〜15万円/月 | 8〜13万円/月 | 10〜20万円/月 | 12〜16万円/月 | 12〜20万円/月 |
👉 他の施設に比べると、有料老人ホームは サービスの自由度が高い代わりに、経済的負担が大きい施設 です。
入居の流れ
- 資料請求・見学(複数施設を比較)
- 入居申込・面談(本人・家族・施設職員による)
- 健康診断書や介護保険証など必要書類を提出
- 入居審査(介護度・医療ニーズ・経済状況など)
- 入居契約(入居一時金・敷金の支払い)
- 入居開始
👉 特養のように待機が長くない反面、「費用負担に耐えられるか」が入居継続の最大のポイント となります。
有料老人ホームの費用相場
有料老人ホームの費用は、月額15〜30万円程度が相場 です。
さらに施設によっては、入居時に数百万円〜数千万円の「入居一時金」が必要になるケースもあります。
特養や老健に比べて高額ですが、その理由は「民間施設ならではのサービスや住環境の自由度」が反映されているためです。
👉 ここでは、有料老人ホームの費用相場を 入居一時金・月額費用・施設タイプ別の違い に分けて整理します。
入居一時金
- 入居時にまとまった金額を支払うシステム
- 数百万円〜数千万円に及ぶこともあり、最大のハードル
- 最近は「0円プラン」や「月払い方式」を導入する施設も増えている
👉 入居一時金は「前払い家賃」のようなもので、長期入居するほどお得になる仕組みですが、短期で退去すると割高になるリスクがあります。
月額費用
有料老人ホームの毎月の費用は 15〜30万円程度 が一般的です。
内訳の目安:
- 家賃(居室料):5〜15万円
- 食費:4〜6万円
- 管理費・共益費:3〜5万円
- 介護サービス費(自己負担):2〜6万円
- 医療費・日用品費:数千円〜数万円
👉 個室や豪華な共用設備を備える施設では30万円以上になることもあります。
施設タイプ別の相場
- 介護付き有料老人ホーム
・相場:20〜30万円/月
・介護サービス費が含まれるため割高 - 住宅型有料老人ホーム
・相場:15〜25万円/月
・介護サービスは外部利用(訪問介護など) - 健康型有料老人ホーム
・相場:15〜20万円/月
・自立高齢者向け。介護が必要になると退去が前提
👉 種類によって「介護費込みか否か」で大きく差が出るのが特徴です。
他施設との費用比較
| 施設種別 | 費用相場(月額) | 入居一時金 |
|---|---|---|
| 有料老人ホーム | 15〜30万円 | 数百万円〜数千万円 |
| 特養 | 12〜15万円 | 不要 |
| 老健 | 8〜13万円 | 不要 |
| サ高住 | 10〜20万円 | 敷金程度 |
| グループホーム | 12〜16万円 | 不要 |
| 介護医療院 | 12〜20万円 | 不要 |
有料老人ホームは、自由度と快適性の代わりに費用が突出して高い施設 と位置づけられます。
有料老人ホームの費用の内訳
有料老人ホームの費用は、入居一時金・月額費用・介護サービス費・医療費 の4つが中心です。
相場だけを見ても実際の支払いイメージが湧きにくいため、内訳を理解しておくことが大切です。
👉 このパートでは、主要な費用項目ごとに詳しく解説します。
入居一時金
- 入居時にまとめて支払う初期費用
- 数百万円〜数千万円に及ぶ場合がある
- 「0円プラン」「月払い方式」が選べる施設もある
- 契約期間が過ぎると償却され、途中退去でも返金されないことが多い
👉 入居一時金は「家賃の前払い」に近い仕組み。
長期的に住むなら結果的に割安ですが、短期退去の場合は負担が大きくなります。
月額費用
入居後に毎月かかる基本費用。
内訳例(介護付き有料老人ホーム・個室の場合):
- 家賃(居室料):8〜15万円
- 食費:4〜6万円
- 管理費・共益費:3〜5万円
👉 合計で 15〜25万円程度
施設の立地・設備・部屋の広さによって差が大きく、都市部の高級施設では30万円を超えることもあります。
介護サービス費(自己負担分)
有料老人ホームで介護サービスを受ける場合、介護保険が適用され、自己負担は1〜3割 です。
- 要介護1:約2〜3万円/月
- 要介護3:約3〜5万円/月
- 要介護5:約5〜6万円/月
👉 所得区分により自己負担が2割・3割となる場合は、費用が倍増します。
「介護付き有料老人ホーム」では月額費用に組み込まれていることが多いですが、「住宅型」の場合は外部サービス利用となり別途発生します。
医療費(自己負担分)
- 定期診察・投薬料:数千円〜1万円/月
- 専門的治療(褥瘡治療、点滴など):数万円追加になる場合も
- 医療費の自己負担は医療保険に基づき1〜3割
👉 有料老人ホームは「医療連携型」ではあるものの、入院治療ほどはカバーされません。
慢性疾患を抱えている方は、医療費が月数万円単位で上乗せされる可能性 に注意が必要です。
有料老人ホームの費用シミュレーション(要介護3・介護付き・一般世帯1割負担)
- 入居一時金:0円(0円プラン選択)
- 月額費用(家賃・食費・管理費):20万円
- 介護サービス費:3.5万円
- 医療費:1万円
👉 合計:約24.5万円/月
入居一時金が不要なプランを選んでも、毎月20万円以上は必要になるケースが多く、特養や老健と比べて高額です。
有料老人ホームの費用を抑えるためのポイント
有料老人ホームは他の介護施設に比べて 費用が高額になりやすい ですが、制度を上手に活用することで自己負担を軽減することが可能です。
ここでは、2026年時点で利用できる主要な方法を整理します。
介護保険制度を最大限に活用する
有料老人ホームでは、介護保険が適用されるサービスを利用することができます。
特に「高額介護サービス費」を利用すれば、介護サービス費の自己負担に上限が設けられます。
- 一般世帯:44,400円/月
- 住民税非課税世帯:24,600円/月
👉 要介護度が高く、介護サービスを多く利用する人ほど効果が大きくなります。
食費・居住費の軽減制度(補足給付)を利用する
住民税非課税世帯で資産要件を満たす場合、食費・居住費の負担を軽減する補足給付 が利用できます。
- 食費:1日1,500円 → 390円(約12,000円/月)
- 居住費:月数万円 → 数千円に軽減される場合もあり
👉 有料老人ホームでも「介護付き有料老人ホーム」であれば対象になります。
医療制度を組み合わせる
介護費に加え、医療費も発生するため 高額療養費制度や高額医療・高額介護合算制度 を活用することで、二重負担を防げます。
- 高額療養費制度 → 月57,600円までに制限(一般世帯の場合)
- 合算制度 → 介護+医療の年間負担に上限を設ける(一般世帯で約56万円/年)
👉 慢性疾患や医療依存度が高い方にとっては大きな負担軽減になります。
自治体の助成制度を調べる
一部自治体では、独自の助成制度を実施しています。
- 食費や居住費への追加助成
- おむつ代助成
- 理美容代助成
👉 小規模でも積み重ねれば年間数万円の差につながります。
入居プランを見直す
- 入居一時金ゼロプランを選択して、初期費用を抑える
- 部屋タイプ(個室 → 相部屋)を変更して、毎月の家賃を節約
- 「介護付き」か「住宅型」かを比較して、介護費込みか別払いかを確認
👉 入居前に複数施設の費用シミュレーションを行うことが重要です。
専門家に相談する
ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することで、制度の申請漏れや適用できる助成の見逃し を防げます。
ポイントまとめ
- 高額介護サービス費で介護費に上限
- 補足給付で食費・居住費を軽減
- 高額療養費・合算制度で医療費もカバー
- 自治体の助成や税控除で追加の節約
- 入居プランを工夫し、専門家に相談することが大切
👉 有料老人ホームの費用は「高い」と感じがちですが、制度と選び方次第で 年間数十万円の差 が生まれます。
介護保険で使える制度
有料老人ホームは民間施設ですが、介護付き有料老人ホーム の場合は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けており、介護保険を利用することができます。
介護サービス費に加えて、特定条件を満たせば 高額介護サービス費や補足給付 といった制度を使い、自己負担を軽減できます。
高額介護サービス費
介護サービス費の自己負担には上限があり、超過分は払い戻されます。
- 一般世帯:44,400円/月
- 住民税非課税世帯:24,600円/月
- 現役並み所得者:140,100円/月
👉 例えば要介護5でサービス費が8万円になっても、一般世帯であれば 44,400円までに制限。
介護度が高いほど効果が大きい制度です。
補足給付(特定入所者介護サービス費)
食費・居住費を軽減するための制度で、介護付き有料老人ホームも対象になります。
- 対象:住民税非課税世帯で資産要件を満たす人
- 軽減例
・食費:1日1,500円 → 390円(約12,000円/月)
・居住費:月数万円 → 数千円程度に軽減
👉 条件を満たせば 月5万円以上の軽減 につながる場合もあります。
介護予防サービス(住宅型・健康型の場合)
住宅型や健康型では介護保険が施設内サービスに直接適用されません。
ただし外部の訪問介護や訪問看護を利用することで、介護保険を活用できます。
👉 「介護付き」か「住宅型」かで制度適用範囲が異なるため、入居前に必ず確認することが大切です。
制度を併用した場合の軽減例
例:要介護3・介護付き有料老人ホーム・住民税非課税世帯
- 食費:45,000円 → 補足給付で12,000円
- 居住費:60,000円 → 補足給付で10,000円
- 介護サービス費:35,000円 → 高額介護サービス費で24,600円
👉 合計で 約14万円 → 約6.4万円/月 に軽減される可能性もあります。
ポイント整理
- 有料老人ホームでも「介護付き」であれば介護保険が適用
- 高額介護サービス費:介護費に上限を設ける
- 補足給付:食費・居住費を大幅に軽減
- 住宅型や健康型では外部サービスで介護保険を利用
👉 制度を正しく理解することで、「高額」と思われがちな有料老人ホームの費用も現実的な範囲に近づけられます。
医療制度との関係(高額療養費・合算制度)
有料老人ホームでは、介護費に加えて 医療費の自己負担 が発生します。
慢性疾患や日常的な診察・投薬が必要な方では、医療費が毎月数万円に及ぶこともあり、介護と医療の二重負担 が大きな問題となります。
そこで活用すべきが「高額療養費制度」と「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。
高額療養費制度(高額医療費制度)
医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
- 対象:国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療制度の加入者
- 上限額(70歳以上・2026年時点)
・一般所得者:57,600円(外来は18,000円)
・住民税非課税世帯:24,600円
・現役並み所得者:80,100円+医療費の1%
👉 たとえば入院や治療で医療費が20万円かかっても、一般世帯なら 57,600円までに制限。
注意点
- 差額ベッド代や食費は対象外
- 「限度額適用認定証」を提示すれば窓口負担を抑えられる
高額医療・高額介護合算療養費制度
介護と医療の両方を利用している世帯に適用され、年間の自己負担に上限を設ける制度 です。
- 仕組み:1年間(8月〜翌7月)の医療+介護の自己負担を合算し、上限を超えた分が払い戻される
- 上限額(2026年時点・世帯単位)
・住民税非課税世帯:約31万円
・一般世帯:約56万円
・現役並み所得世帯:約212万円
👉 例:介護費40万円/年+医療費30万円/年 → 合計70万円
一般世帯の上限56万円を超えるため、14万円が払い戻される 仕組みです。
制度の組み合わせによる効果
- 高額療養費制度:月単位で医療費に上限
- 高額介護サービス費:月単位で介護費に上限
- 合算療養費制度:年間トータルでの上限
👉 この3つを組み合わせることで、有料老人ホームで発生しがちな「介護+医療の二重負担」を大幅に軽減できます。
ポイント整理
- 有料老人ホームでは介護費だけでなく医療費も発生
- 高額療養費制度:1か月の医療費に上限
- 合算療養費制度:1年間の介護+医療費を合算して上限設定
- 制度を併用すれば、医療依存度が高い方でも安心して入居可能
👉 制度を知らずに支払っているケースも多いため、必ずケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーに確認することが重要 です。
自治体の独自助成制度
有料老人ホームの費用は、国の介護保険や医療制度である程度カバーできますが、自治体独自の助成制度 を利用すれば、さらに自己負担を減らせる可能性があります。
制度内容は市区町村ごとに異なり、知らずに使い漏れているケースも少なくありません。
利用者負担軽減制度(自治体版)
- 一部自治体では、低所得者を対象に介護サービス費の自己負担を軽減
- 内容:自己負担を25〜50%軽減
- 対象:住民税非課税世帯、生活困窮世帯(資産要件あり)
- 申請窓口:市区町村の介護保険課
👉 高額介護サービス費と組み合わせて利用できる場合もあり、月数万円の軽減につながることがあります。
食費・居住費への追加助成
国の「補足給付」で対象外となった人を支援するために、独自助成を行っている自治体もあります。
例:
- 横浜市:介護サービス自己負担助成
- 神戸市:「利用者負担軽減確認証」を発行
- 東京都23区の一部:生活困窮高齢者への食費・居住費補助
👉 「国の制度で救済されない人」を支援するセーフティネットとして重要です。
生活支援型の助成制度
介護費用そのものではなく、日常生活に関わる費用を補助する仕組みもあります。
- 紙おむつ代助成(毎月数千円)
- 理美容代助成
- 通院交通費助成
- 福祉用具購入補助
👉 有料老人ホーム入居者でも対象になることがあり、年間で数万円の節約になります。
社会福祉法人の軽減制度
社会福祉法人が運営する有料老人ホームでは、独自に費用軽減制度を設けている場合があります。
- 介護サービス費の自己負担を軽減(1割 → 0.5割など)
- 運営法人に直接申請が必要
👉 入居を検討する際には、その施設の法人独自制度を確認することが大切です。
自治体制度を調べる方法
- 市区町村役所の 介護保険課・高齢福祉課 に相談
- 自治体の公式サイトで「介護 費用 軽減」「高齢者 福祉制度」などを検索
- 入居予定の施設に直接確認(施設が制度を把握している場合も多い)
ポイント整理
- 自治体の独自助成は「国の制度の隙間」を補うもの
- 食費・居住費・日常生活費の軽減につながる
- 社会福祉法人独自の軽減制度も見逃せない
- 制度を調べる際は「役所+施設+公式サイト」の3方向で確認
👉 小さな助成でも積み重ねれば、年間数万円〜十数万円の負担軽減 につながります。
まとめ:有料老人ホームの費用は制度を組み合わせて抑えられる
有料老人ホームは、自由度が高く快適な生活を提供する一方で、月額15〜30万円+入居一時金 と費用が高額になりやすい施設です。
特養や老健と比べると経済的負担が大きく、入居をためらうご家族も少なくありません。
しかし、ここまで紹介してきたように、介護保険・医療制度・自治体助成を活用すれば、自己負担を大幅に軽減できる可能性 があるので、制度を使い倒せば現実的な選択肢 になります。
ポイントまとめ
- 費用相場:月額15〜30万円、入居一時金は数百万円〜数千万円
- 費用内訳:入居一時金・月額費用・介護サービス費・医療費
- 費用を抑えるポイント:
・高額介護サービス費 → 介護費に上限
・補足給付 → 食費・居住費を軽減
・高額療養費・合算制度 → 医療+介護の二重負担を防ぐ
・自治体助成・法人独自制度 → さらに追加の軽減
・入居プランの工夫・ケアマネ相談 → 見逃し防止
👉 大事なのは:
- 入居前に 複数施設を比較し、費用シミュレーションを行うこと
- 介護保険・医療制度・自治体助成を すべて確認して申請漏れを防ぐこと
- 家族全体で資金計画を立て、無理のない入居を実現すること
費用面の不安を解消し、家族にとって最適な住まいを選んでいきましょう。