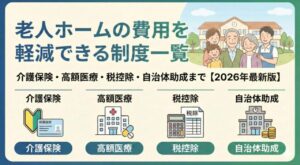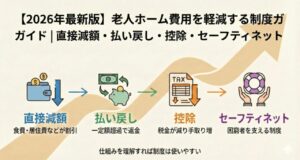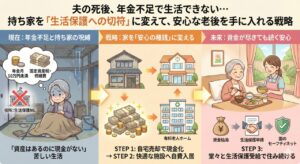医療保険の仕組みや制度を正しく理解していますか?
この記事では、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の違いや対象者、自己負担割合、高額療養費制度の活用法までをやさしく解説します。
医療費負担を軽減し、安心して治療を受けるためのポイントをまとめた保存版ガイドです。
お金の心配を減らして、治療・療養に集中できる環境を整えましょう。
医療保険とは?|すべての人が加入する「国民皆保険制度」
日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての国民がいずれかの医療保険に加入しています。これは、病気やけがの治療費が一部負担で済むように設計された、いわば「安心のセーフティネット」です。
- 健康保険(会社員・公務員)→ 協会けんぽ・健康保険組合
- 国民健康保険(自営業・無職)→ 市町村が運営
- 後期高齢者医療制度(75歳以上)→ 都道府県の広域連合
誰でも加入必須。どこで働いているか、何歳かによって保険の種類が変わります。
医療保険の種類と対象者
健康保険(会社員・公務員など)
- 協会けんぽや健康保険組合が運営
- 家族(被扶養者)も一緒に保障される
国民健康保険(自営業・フリーランス・退職者)
- 市町村が運営
- 所得に応じて保険料が決定
後期高齢者医療制度(75歳以上)
- 原則75歳から自動的に移行
- 所得に応じて1~3割の負担に
保険証を見れば、自分がどの制度に入っているか一目で分かります。
医療保険でカバーされる主なサービス
基本的には「保険医療機関」への受診などで「保険診療」を受けることが出来ます。
怪我や病気で受診する病院やクリニックは保険診療となります。
美容整形などの「自由診療」では医療保険は使えず、自費で支払うことになります。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 外来診療 | 診察・検査・薬の処方 |
| 入院治療 | 手術・投薬・リハビリ |
| 訪問診療 | 医師が自宅を訪問し診察 |
| 高額療養費制度 | 一定以上の医療費が戻ってくる |
| 傷病手当金 | 病気・ケガで休職中の生活保障(会社員向け) |
| 出産育児一時金 | 出産時の補助金制度 |
| 特定疾病療養費 | 人工透析など高額治療の負担軽減 |
自己負担の割合と年齢別の違い
70歳を超えると2割や1割になりますが、69歳以下は3割負担となります。
また、70歳以上の方でも「所得が多い方」は負担割合が増加し3割負担となる場合もあります。
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 75歳以上 | 1〜3割(後期高齢者医療制度) |
| 70〜74歳 | 2〜3割 |
| 69歳以下 | 3割が基本 |
高額療養費制度とは?

病気や手術で医療費が高額になったときでも、「高額療養費制度」を使えば、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
所得によって負担上限額が決まったおり、所得が多い人はたくさん払い、所得が少ない人は自己負担額も少なくなります。
74歳以下(健康保険・国民健康保険)
| 所得区分 | 自己負担上限(月額) | 多数回該当※ |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円~(区分ア) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(上限140,100円) | 140,100円 |
| 年収約770~1,160万円(区分イ) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(上限93,000円) | 93,000円 |
| 年収約370~770万円(区分ウ) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(上限44,400円) | 44,400円 |
| 年収~約370万円(区分エ) | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯(区分オ) | 35,400円 | 24,600円 |
- 多くの人が「区分ウ」か「区分エ」に該当します。
- 扶養家族がいる方も、医療費の合算が可能なケースがあります。
75歳以上(後期高齢者医療制度)
| 所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担上限(月額) (外来/外来+入院) | 多数回該当※ |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(上限140,100円) | 140,100円 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 3割 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(上限93,000円) | 93,000円 |
| 現役並み所得者Ⅰ | 3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(上限44,400円) | 44,400円 |
| 一般(課税世帯) | 1〜2割 | 外来:18,000円/外来+入院:57,600円(年間上限:144,000円) | 14,000円 |
| 低所得者Ⅱ | 1割 | 外来:8,000円/外来+入院:24,600円 | 8,000円 |
| 低所得者Ⅰ | 1割 | 外来:8,000円/外来+入院:15,000円 | 8,000円 |
- 一般・低所得者の方は「外来のみ」と「外来+入院(世帯単位)」で上限が異なります。
- 入院がある場合は、世帯単位の上限を適用し、より負担が軽減されます。
- 高所得者でも4回目以降の多数回該当で自己負担上限が軽減されます。
高額療養費制度を利用する方法
方法①:事前に「限度額適用認定証」を申請する(おすすめ)
- 加入保険の窓口(市役所、協会けんぽ、健康保険組合など)に申請
- 認定証を病院窓口に提示→支払い時に上限が自動適用!
方法②:医療費を支払ったあとに申請し、払い戻しを受ける
- 病院や薬局で通常通り支払う
- 約3カ月後、加入している医療保険の保険者に申請
▶ 申請先の例:
- 国民健康保険 → 市区町村の役所・国保課
- 協会けんぽ → 全国健康保険協会
- 健康保険組合 → 各組合の窓口・会社の総務課
- 後期高齢者医療制度 → 都道府県の広域連合窓口
医療保険と介護保険の違い
医療保険は全年齢に関係があり、病気や怪我をした時に使う国民全員が使える制度です。
介護保険は介護が必要な人が使う制度で、65歳以上の介護が必要な状態の方もしくは40歳以上の特定の病気で介護が必要になった方が使える制度になります。
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 目的 | 病気・けがの治療 | 生活支援・介護サービス |
| 対象者 | 国民全員 | 65歳以上/40歳以上(特定疾病) |
| 主な内容 | 外来・入院・訪問診療 | 訪問介護・デイサービスなど |
| 自己負担 | 1〜3割(上限あり) | 1〜3割(支給限度あり) |
よくある質問
- 入院時に医療保険だけで足りますか?
-
医療保険は診療・治療費をカバーしますが、食事代・差額ベッド代・日用品などは自己負担となります。
長期入院の場合は、高額療養費制度の活用や民間保険で備えると安心です。 - 高額療養費の申請はいつまでにすればいいですか?
-
支払日の翌日から2年以内であれば申請可能です。早めに申請したほうが払い戻しが早く受けられます。
- 「限度額適用認定証」はどこで申請できますか?
-
加入している保険(協会けんぽ、市区町村の国保、健康保険組合、後期高齢者医療制度など)の窓口で申請できます。1週間程度で届くことが一般的です。
- 医療費と薬代は合算して高額療養費制度の対象になりますか?
-
はい、同じ月内であれば「医療費+薬局で支払った薬代」を合算して上限判定されます。複数の医療機関を受診してもOKです。
- 家族の医療費も合算できますか?
-
同じ健康保険に加入している家族(世帯)であれば合算できます。世帯全体の負担が大きいときは特に有効です。
- 医療保険と介護保険は同時に使うことはできますか?
-
はい、可能です。たとえば「病気の治療は医療保険」「生活支援や介護サービスは介護保険」というように、目的ごとに使い分けられます。
ダウンロードして使える図解・早見表
スマホでの閲覧や、家族への共有に便利です。ご自由にご活用ください。
まとめ|医療保険は正しく使えば安心の制度
- 医療保険は全員加入。内容を知っておくことが安心への第一歩
- 自己負担は年齢と所得で異なる。高額療養費制度で負担軽減
- 「限度額適用認定証」の取得で支払いがラクに!
- 医療保険と介護保険は併用可能。対象や制度の違いを理解しよう
制度を知っているかどうかで、医療費の負担や安心感は大きく変わります。
特に高額療養費制度や限度額適用認定証は、入院や長期治療時に家計を守る強い味方です。
この記事をきっかけに、ご自身やご家族の保険内容を確認し、必要な手続きを事前に整えておくことをおすすめします。