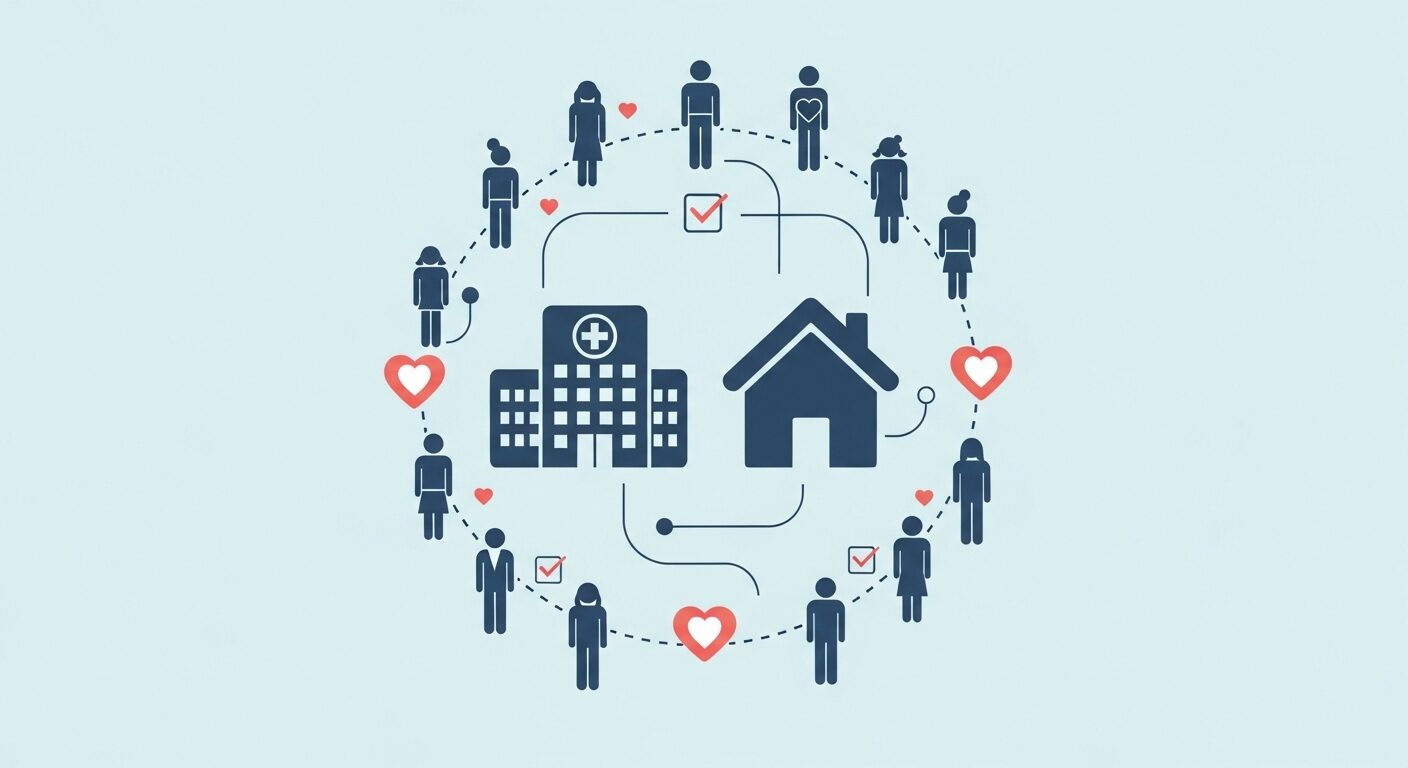「急性期病院で退院調整を進めたいが、身元保証人が見つからない…」「施設入所が決まらない理由が“保証人なし”の一言で済まされる」
そんな悩みに日々直面しているケアマネージャーや医療ソーシャルワーカーの皆さんも多いのではないでしょうか。
厚生労働省のデータによれば、単身高齢者や高齢夫婦のみの世帯は年々増加しており、令和2年時点で約3割に達しています(※厚労省「令和2年 国民生活基礎調査」より)。
それに伴い、入院・施設入所に際しての「保証人がいない」問題は、もはや特殊なケースではなく日常的な課題となっています。
この記事では、現場職としてすぐに実践できる「4つの対応策」を、具体例とともにご紹介します。
対応策①:家族・親族への再アプローチと説明の工夫

まず最初に考えるべきは、本人の了承を得たうえでの親族等への再アプローチです。
「保証人になりたくない」という家族の背景には、以下のような不安が潜んでいることがあります。
- 経済的負担が発生するのでは?
- 万が一の際、自分が責任を負うのか?
- 曖昧な説明で内容が理解できない
こうした不安に対し、医療同意や支払い義務の範囲について具体的かつ簡潔に説明することで、納得してもらえるケースもあります。
たとえば、「医療同意はあくまで本人が判断困難な場合に限られる」「費用の請求は本人に対して行われる」など、正確な情報提供が鍵です。
対応策②:地域包括支援センターや成年後見制度の活用

保証人が見つからない場合、地域包括支援センターを通じた相談や行政支援制度の活用が有効です。
なかでも注目したいのが、「成年後見制度(法定・任意)」です。
| 分類 | 利用対象 | 主な機能 | 申立先 |
|---|---|---|---|
| 法定後見 | 判断能力が低下している高齢者等 | 財産管理・身上保護 | 家庭裁判所 |
| 任意後見 | 判断能力があるうちに契約 | 財産・医療など幅広く指定可 | 将来的に効力発生 |
ただし、制度の開始までに時間がかかるため、早めのアセスメントと連携が必要です。
対応策③:NPO・民間保証サービスの検討

近年は、高齢者の身元保証を支援するNPO法人や民間サービスも増えています。
代表的なものとして以下のような団体があります:
- 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
- 高齢者支援を専門とする地域NPO
- 民間身元保証サービス会社(※一部では医療・介護連携も可能)
過去に独居高齢者の方が入院される際、民間の保証団体を活用しスムーズに入院受け入れができたケースがありました。
医療側・家族・保証人の三者がしっかりと連携できる仕組みが整っている団体を選ぶのがポイントです。
こうしたサービスは、金銭的な負担や支援範囲、緊急時対応の体制に差があるため、事前にパンフレットや公式サイトなどでの確認が重要です。
対応策④:院内・施設内での「支援同意体制」の構築

最終手段として、院内や施設内でのリスクマネジメント体制を整えるという方法があります。
- 施設長名義での入所契約・同意取得
- 医療チームによる判断と記録の明確化
- 看取りや延命処置に関する意向の可視化
もちろん、法的責任や家族からの苦情リスクを最小限にする必要がありますが、現場として“受け入れを止めない”工夫が問われる局面も増えています。
おわりに:孤立を防ぐ「つなぎ役」としての支援を
身元保証人の不在は、制度の不備というよりも「社会の構造的課題」です。
だからこそ、ケアマネやMSWなど現場の専門職が果たす役割は、単なる手続きの代行にとどまりません。
本人の尊厳を守り、支援の輪を広げる“つなぎ役”として、確かな情報と判断力が求められます。
身元保証に関するご相談【東海エリア限定】
私達は「身寄りがなく、入院や施設入所が不安」「医療同意をしてくれる人がいない」
このようなお悩みに、看護師としての経験を活かした支援をご提供しています。
医療機関とのやり取りや急変時の判断についても、看護師の立場から丁寧にご説明・ご対応します。
生活支援・死後事務委任・医療同意など、複雑な手続きもご本人とご家族に寄り添いながら一緒に考えてまいります。
少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。