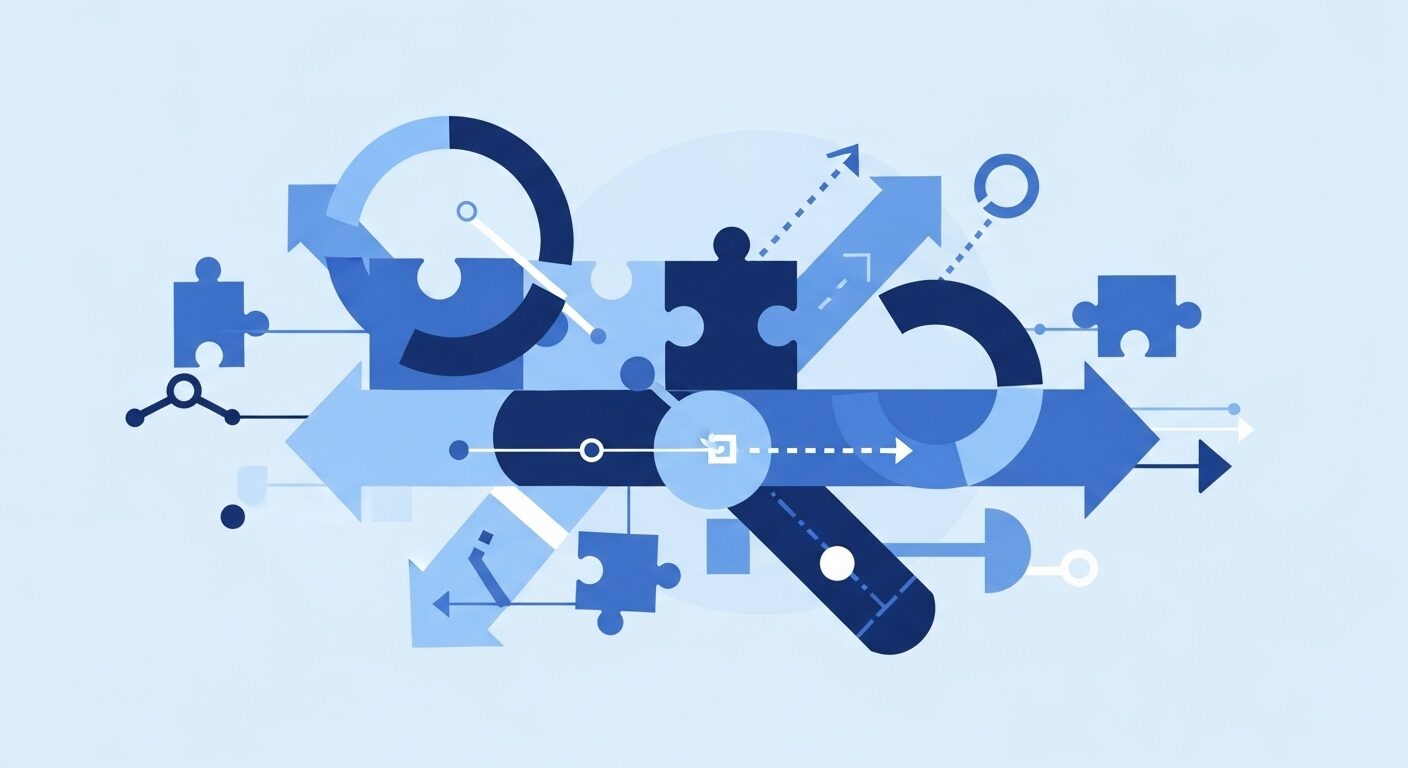はじめに|「うまく連携できていない」と感じるときに読んでほしい

「訪問看護と診療で情報がずれている」「ケアマネに伝えたつもりが伝わっていなかった」…
在宅医療の現場で働くと、こうした“すれ違い”に日常的に直面します。
それぞれが専門性を発揮しているにもかかわらず、連携不足によって支援の質が落ちたり、ご本人やご家族に不安を与えてしまうのはとても残念なことです。
この記事では、訪問診療と訪問看護・ケアマネ間で起きやすい「連携のすれ違い」を具体的に掘り下げ、現場で実践できる対策を紹介します。
よくあるすれ違い①|訪問診療と訪問看護の情報共有の壁

指示書はあるけれど、情報が足りない
訪問診療と訪問看護は医療の両輪ですが、情報共有は「指示書のみ」というケースが多くあります。
しかし実際には、「どういう意図でその指示が出たのか」「どのくらいの頻度で様子を見てほしいのか」といった、文面に表れない部分が大切です。
また、FAXでのやりとりが中心の事業所では、情報の時差が生じやすく、診療時点では看護側の新しい情報が届いていないことも。
訪問看護側が困ること
- 指示の背景が読み取れず、緊急時の判断が難しい
- 訪問診療の報告書が届かず、全体像が把握できない
- 状態変化があっても、次の診療日が数日先で不安
訪問診療側が困ること
- 看護記録が主観的で、医学的判断につなげづらい
- 看護師と直接話せるタイミングが限られ、双方向性に欠ける
よくあるすれ違い②|訪問診療とケアマネの認識ズレ
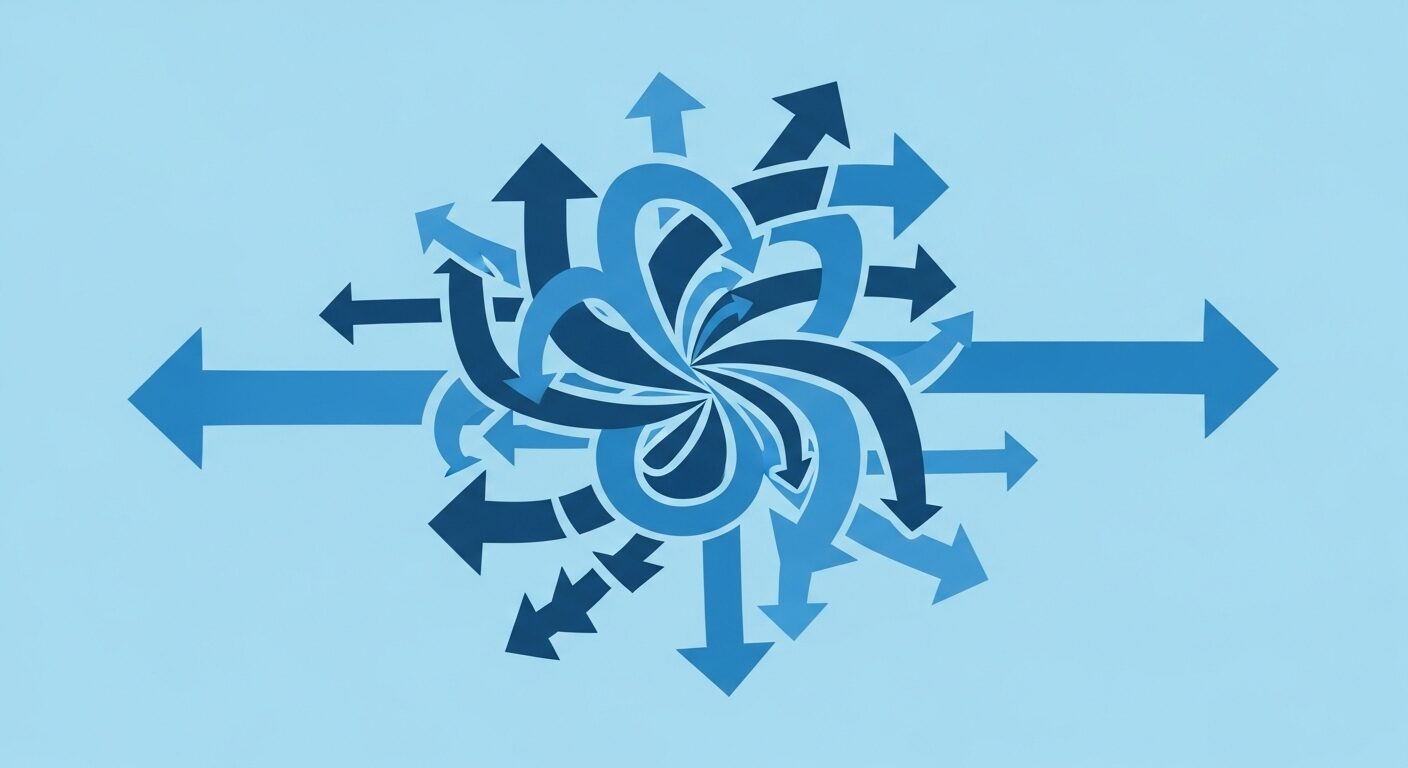
「誰が全体を見ているのか」が不明確
在宅ケアは多職種の連携で成り立ちますが、それぞれが“自分の視点”だけで動いてしまうと、全体の調和が崩れます。
医療側は病状や処方を重視し、ケアマネは生活支援や在宅維持を重視します。方向性が共有されていないと、「話が合わない」「協力しづらい」という印象を持ってしまいます。
プラン変更や指示変更の情報が届かない
例えば、訪問診療で急な薬変更があっても、ケアマネがそれを知るのはモニタリング訪問時ということも。
その間に生活状況が変わっていても気づけず、介護サービスの見直しが遅れます。
すれ違いを防ぐための3つの対策
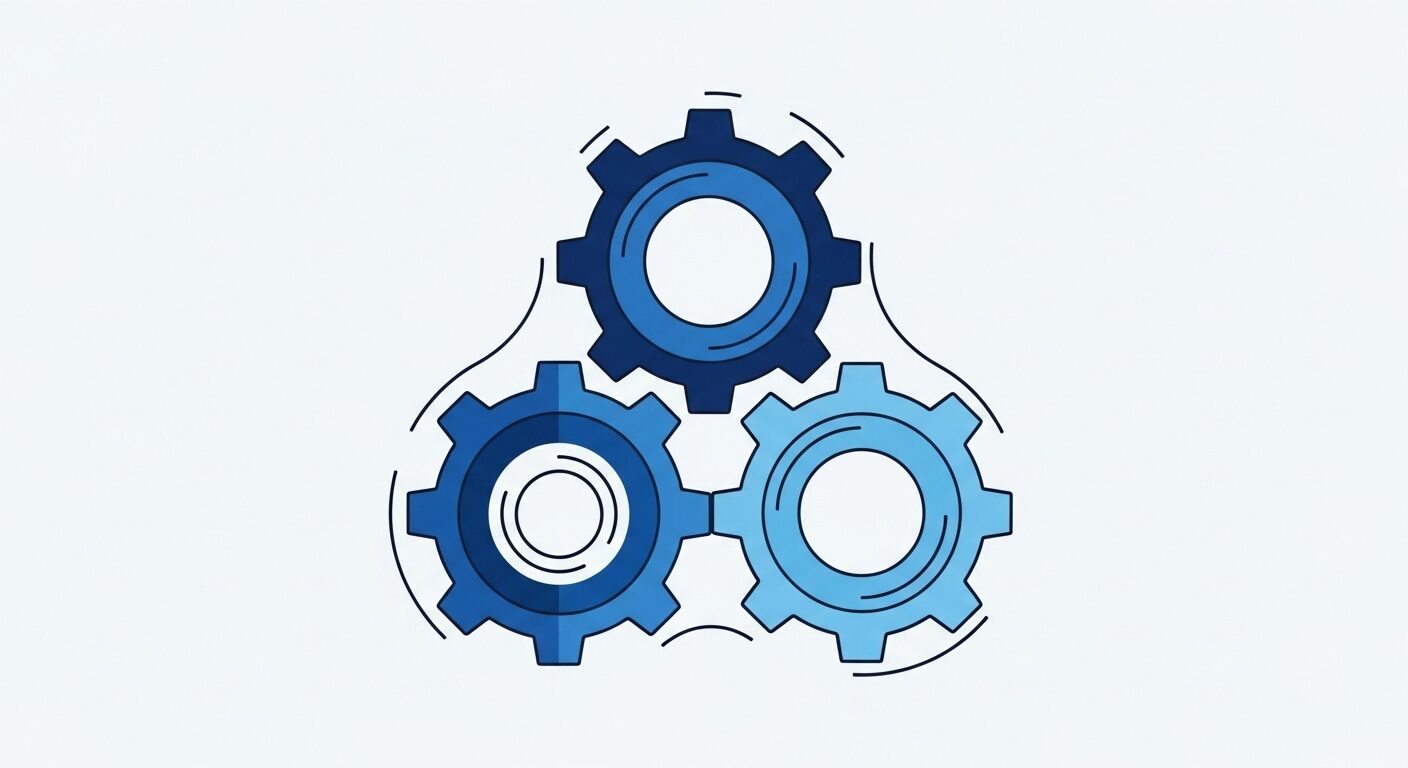
1. タイムリーな情報共有を「仕組み」で整える
いまやLINEやSlackなど、情報共有ツールは多様です。セキュリティ面のルールを守りつつ、「訪問後の簡易報告」や「状態変化の速報」をチャット形式で共有するだけでも、連携精度は格段に上がります。
2. ゴールの共有と役割の見える化
本人がどんな暮らしを望んでいて、それを医療的・介護的にどう支えるか。
初回カンファレンスでしっかり共有し、各職種の役割・責任範囲を明文化することが重要です。
また、結論だけでなく、「なぜこの指示を出したのか」、「なぜこの報告をしているのか」などの
「経過も詳しく伝える」ことで、それぞれの意図や目指したい目標が明確になってくると思います。
更に、モニタリング・再カンファで定期的に方向性を確認し直す仕組みがあると安心です。
3. “連携の主語”を「本人」に戻す
医療の視点、介護の視点、それぞれ大事ですが、主語が「自分たち」になっていないかの見直しは大切です。
「この人にとって、今のこの方針がベストなのか?」という問いを常にチームで持ち続けることで、連携は自然と前向きになります。
現場の声|こんなすれ違いがありました
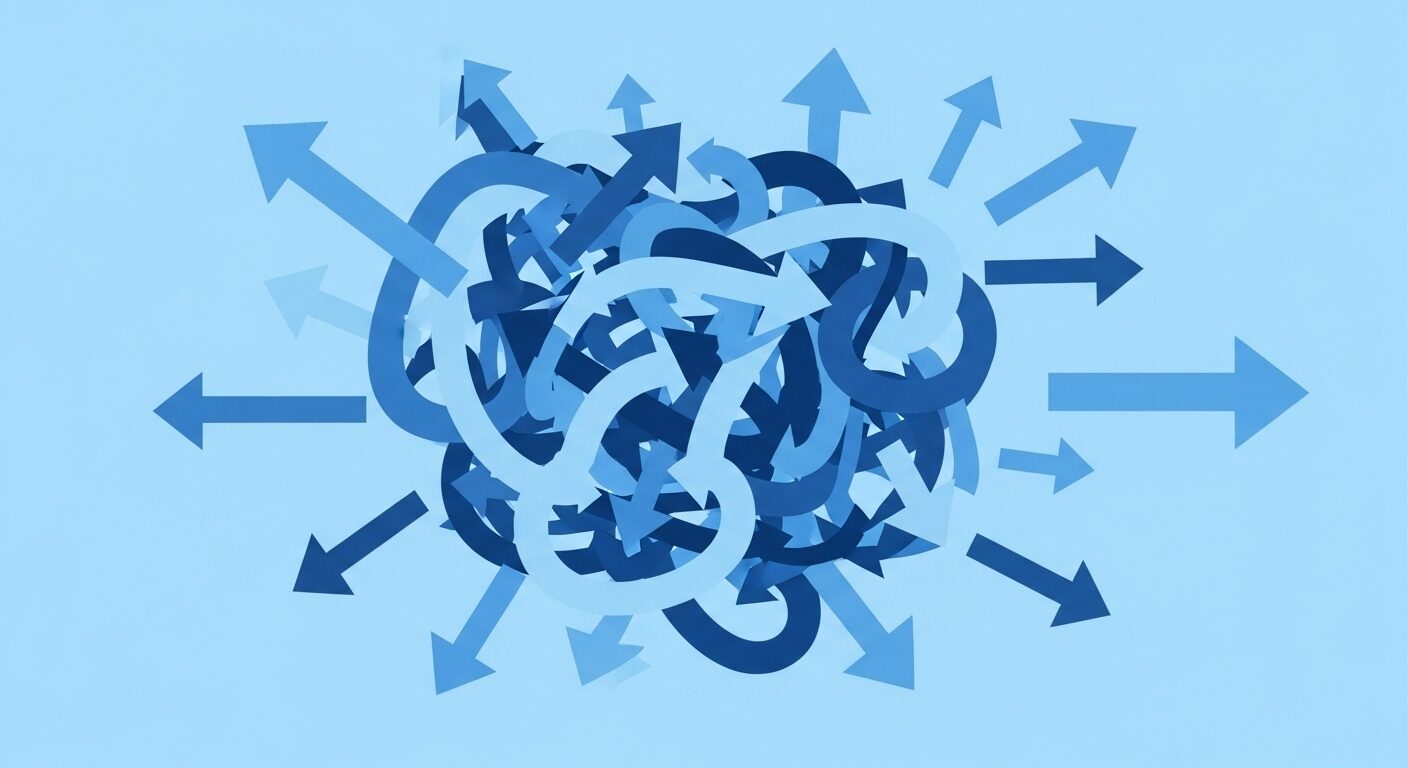
よくある質問(FAQ)

A.急変や状態変化、薬剤変更、家族の希望などは即時連絡が必要です。報告フォーマットを作っておくと負担なく共有できます。
A.基本的にはケアマネが全体調整役ですが、診療側が支援方針を示している場合は医師主導での調整も検討を。
A.診療情報提供書や指示書など、本人・家族の同意がある場合は共有可能。地域によっては「同意書様式」の活用が有効です。
まとめ|「すれ違い」は仕組みで減らせる
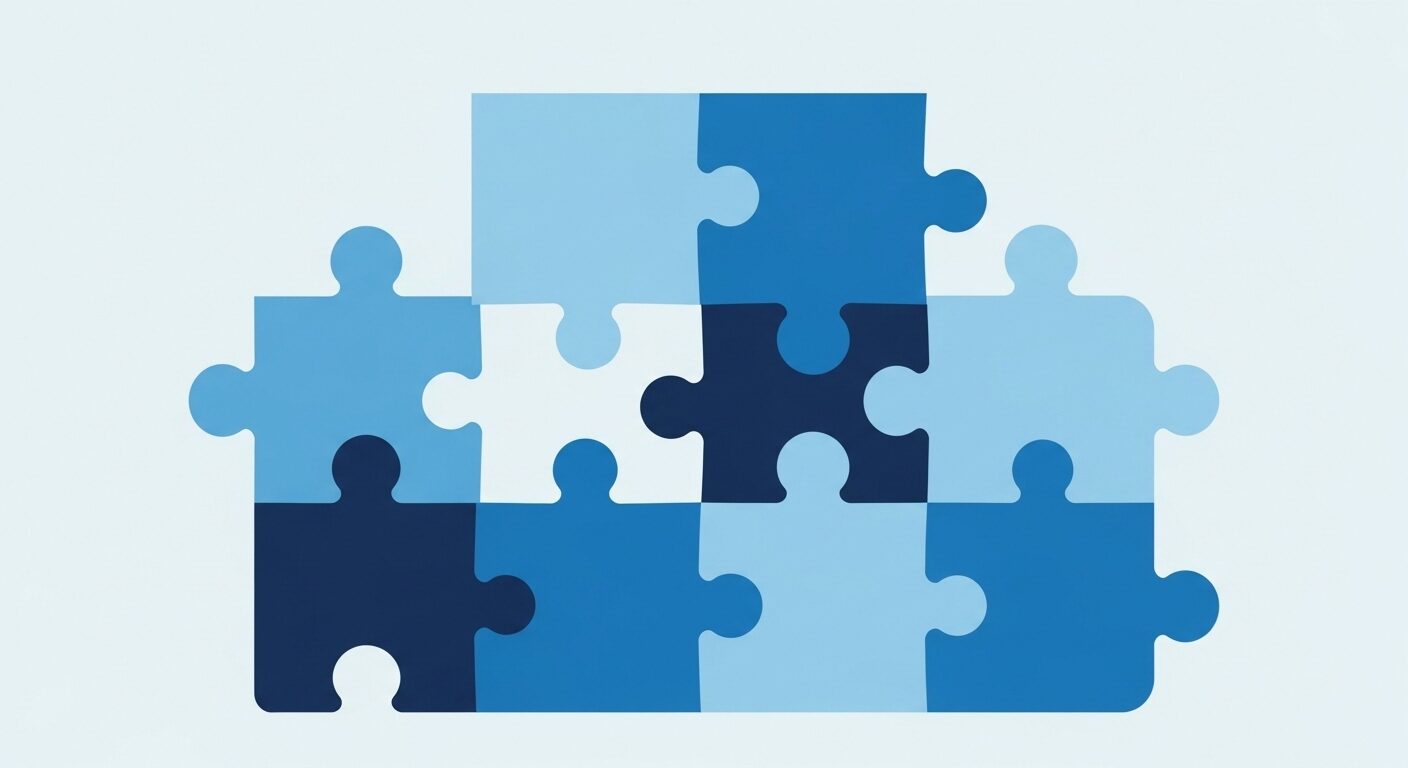
訪問診療と訪問看護、ケアマネの連携は、在宅ケアの質を左右する重要な要素です。
どの職種も忙しい中、情報が届かない・共有されないまま業務が進んでしまうと、結果として本人や家族に不安を与えてしまいます。
小さな工夫や確認のひと手間が、連携の質を大きく変えます。
ぜひ、この記事で紹介した「情報共有の仕組み化」「役割の見える化」「本人中心の視点」を、現場で取り入れてみてください。